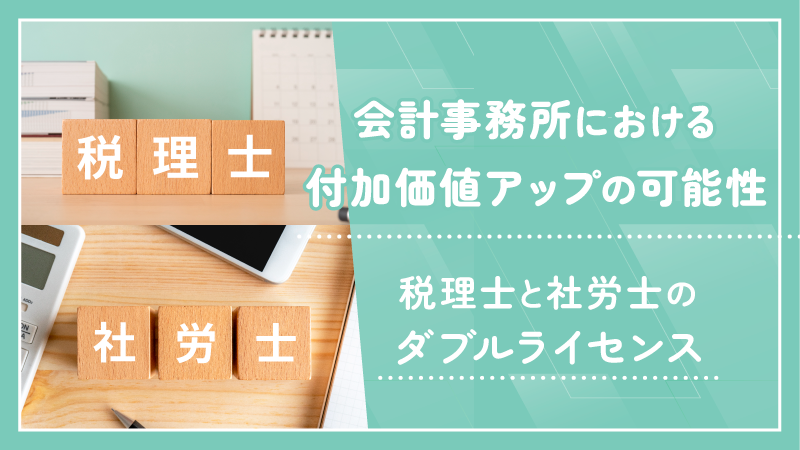顧問先からのニーズが多様化するなか、税理士や会計事務所が社労士(社会保険労務士)の専門性を取り入れることは、事務所の付加価値アップ、他事務所との競争力強化につながります。この記事では、社労士との連携によるワンストップサービス、また税理士と社労士のダブルライセンスの可能性やメリットについて、詳しく解説します。
この記事の目次
税務と労務は、企業経営において切っても切れない領域です。
しかしそれぞれに高い専門性が求められることから、関係のない税理士事務所と社労士(社会保険労務士)事務所がそれぞれ担当するケースが多く見られます。
そうしたなか、会計事務所としての付加価値を高めるべく、グループ内に社労士事務所を開設する税理士法人もあります。
経営課題としての「労務」への関心が高まるなか、社労士資格を持つダブルライセンスの税理士や、税理士法人と社労士法人を併設するグループによる“ワンストップサービス”の提供は、他事務所との差別化の点でひとつの武器になり得ます。
本記事では、税理士が社労士資格を取得する意義や、税理士法人と社労士法人の連携がもたらすメリットについて詳しく解説します。
社労士の活躍できるフィールドが広がっている
働き方改革と法改正が追い風に
2018年にスタートした働き方改革関連法により、長時間労働の是正や有給休暇の取得義務化、同一労働同一賃金、中小企業の割増賃金率の引き上げ、派遣労働者の待遇改善、高年齢者就業確保措置(70歳までの就業機会確保)などが次々と施行されました。
施行により、企業の労務リスクに対する意識は以前よりも確実に高まっています。
労務手続きの電子申請義務化、社会保険の適用拡大などもあり、企業が遵守(じゅんしゅ)すべき労務関連の法令は年々複雑化・高度化してもいます。
こうした背景から、人事労務の専門家である社労士への企業のニーズはますます高まっているのです。
経営課題としての「労務」が注目されている
労働関連法の改正に加え、従業員の定着や生産性の向上、多様な働き方への対応といった観点からも、労務管理は経営に欠かせないテーマになりました。
こうしたなかで、会社の”会計”の視点から経営支援を行うだけでなく、会社の”労務”の視点からも経営支援を行えることは、会計事務所・税理士法人にとっては顧客への付加価値提供につながります。
税理士と社労士双方の専門性を生かした包括的な支援体制を求める企業は、今後ますます増えていくと考えられます。
助成金支援の役割も高まる
企業向けの助成金活用の支援においても、社労士の活躍のフィールドは広がっています。
感染症拡大の時期にも注目された助成金は、厚生労働省が管轄し、雇用関係や労働環境の改善に対して支給されるもので、代理申請は社労士にしか行えません。
2025年現在でも、中小企業が活用を検討すべき助成金は、「業務改善助成金」「キャリアアップ助成金(賃金規定等改定コース)」「働き方改革推進支援助成金」などさまざまなものがあり、制度の内容や申請要件は実に複雑です。
助成金の内容を正確に把握し、適切な活用を提案できる社労士の役割が重要になっているのです。
税理士が社労士資格を取るメリット
社労士と税理士、それぞれの役割
税理士の主な役割は、法人税・所得税・消費税などの申告業務、記帳代行、経営分析・資金繰り支援、税務調査対応、税務コンサルティングなどです。
一方で社労士は、労働社会保険手続、就業規則の作成、労務相談、給与計算、助成金申請などを行う専門職です。
それぞれの資格には“独占業務”が定められており、税理士は「税務代理」「税務書類の作成」「税務相談」、社労士は以下の「一号業務」と「二号業務」が独占業務として法令で規定されています。
【社労士の独占業務】
- 「一号業務」は、労働社会保険諸法令に基づく申請書、届出書、報告書、審査請求書、再審査請求書などの作成と提出の代行。つまり、行政機関への提出書類の作成や当事者の代理人業務
- 「二号業務」は、労働社会保険関連の法令に基づく帳簿書類の作成。企業が持っておくべき、労働者名簿、賃金台帳、出勤簿という3つの帳簿(いわゆる「法定三帳簿」)の作成
※なお、事業における労務管理その他の労働に関する事項及び労働社会保険諸法令に基づく社会保険に関する事項について、相談に応じ、または指導する「三号業務」は独占業務にはあたりません
つまり、税理士が労務の手続きを代行したり、社労士が税務申告を行ったりすることは法律上できないのです。
顧客に“ワンストップサービス”を提供できる
税理士と社労士の業務領域は異なりますが、給与計算や年末調整の場面などで密接に関わり合ってもいます。
こうした実務上の接点において、両資格の知見を生かした対応ができれば、業務の正確さや効率が大きく向上します。
顧客企業としても、税理士と社労士との密接な連携体制やダブルライセンスの税理士によって、税務・労務両面からのアドバイスを一括して受けられ、コスト削減や業務効率化が進みます。
会計事務所にとっても、それが他事務所との大きな差別化になるのです。
ただし法律上、会計事務所単体ではすべての「社労士業務」は行えない
社会保険労務士法により、「外部の顧客企業への」社労士業務の提供は、社労士事務所または社労士法人を通じてのみ認められています。
ただし、税理士が行える社労士関連の業務も存在します。
全国社会保険労務士会連合会と日本税理士会連合会の間で確認書が締結され、「租税債務の確定に必要な事務」、つまり税理士業務に付随して行う計算や書類作成といった社労士業務を税理士が行うことは、認められました。
また、会計事務所に所属する社労士か、社労士とのダブルライセンスを持つ税理士が、事務所内で社労士業務を行うことも社労士法違反にはなりません。
社会保険労務士法で独占業務に定められている「一号業務」「二号業務」を、会計事務所単体で「外部の顧客企業に」提供はできないということなのです。
税理士による社労士業務の提供方法
1. ダブルライセンスの税理士がグループ内の社労士事務所を兼務する
1つは税理士法人に所属しつつ、グループ内の社労士法人でも社労士業務を提供する形です。
もう1つは、「~税理士・社労士事務所」といった形で、事務所の組織体制を見直すという選択肢もあります。
これらの形態であれば、法的な問題をクリアした上で顧客に労務サービスの提供ができるようになります。
2. ほかの社労士事務所と連携する
自らは税理士事務所に所属しつつ、提携先の社労士事務所と共同で案件に対応するスタイルです。
たとえば給与計算における税務処理は税理士側で行い、社会保険の手続は社労士事務所側が行うなど、役割を明確に分担して連携することで、ワンストップでの顧客支援が提供できます。
3. あくまで知識として活用する
税理士が社労士資格を取得していても、社労士業務の提供は行わず、あくまで税務支援や顧問先への助言に生かすという方法もあります。
たとえば就業規則の見直しの際に労務知識を踏まえたアドバイスができるなど、あくまで税理士の専門性を補強する形で活用する場合です。
税理士試験と社労士試験の違い
税理士試験と社労士試験は、試験制度や出題範囲に大きな違いがあります。
税理士試験は、11科目から希望の科目を選択して合格すると、翌年の受験以降合格科目の試験が生涯免除となる、「科目合格制」が認められています。
社労士試験は、8科目すべてに同時に合格する必要があります。 労働基準法、健康保険法、厚生年金保険法、国民年金法、労働保険徴収法、労働安全衛生法などの幅広い科目に一度に合格する必要があるのが、税理士試験との大きな違いです。
まとめ
社労士業務を扱い、税務と労務のワンストップサービスを提供することは、会計事務所として新たな付加価値を提供する有力な方法です。
社労士を採用したり、税理士が自ら社労士資格を取得したりして社労士事務所を併設するのも、付加価値提供のひとつの形といえます。
また、社労士事務所を併設しなくとも、有力な社労士と密に連携できればクライアントへの価値提供は可能です。
同時に、会計事務所の付加価値提供の方向性は労務だけではありません。
顧客の経営に深く入り込み、顧客の経営改善を行うことや、補助金申請などの行政書士よりのサービスを提供することもできます。
【顧客の経営改善・利益創出メソッドの例】
KUROJIKA式・顧客の利益創出メソッド①:会計人に問われる「本当に価値のある顧客支援とは」【PR】
大切なのは、自身に合う付加価値提供の方法を考え、サービスを拡張することです。
【社労士関連の記事ではこちらもおすすめ】
社会保険労務士の需要は今後どうなる?AIでなくなるって本当?現状と将来性を解説
「社会保険労務士はやめとけ」と言われるのはなぜ?資格のメリットや働き方について解説
【2025年最新】社労士と税理士の徹底比較!仕事内容・年収・難易度から適性まで解説
社労士試験の難易度は?6つの資格との比較や、独学での勉強法も紹介!
【参考記事】
https://www.ibaraki-sr.com/FAQ
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000148322.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/index_00057.html
https://www.shakaihokenroumushi.jp/Portals/0/resources/knight/
https://www.nta.go.jp/taxes/zeirishi/zeirishishiken/gaiyo/gaiyou.htm
https://www.sharosi-siken.or.jp/about/outline/